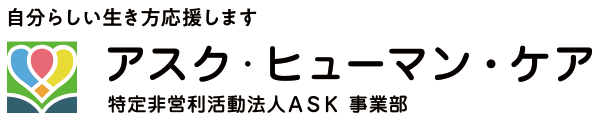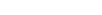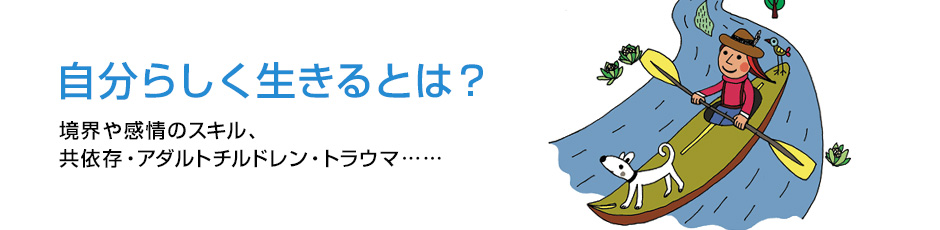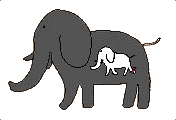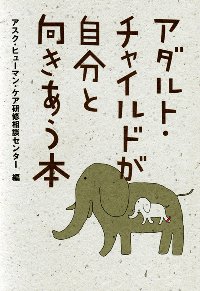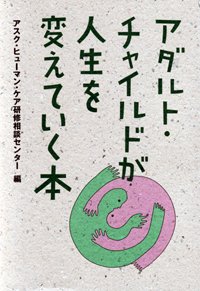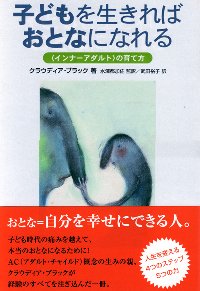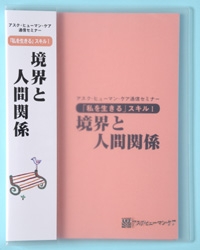アダルトチルドレン(AC)とは
このページを開いてくださったあなたに。
ようこそいらっしゃいました。
水澤都加佐です。
いま私は、あなたがどのような気持ちでこのページを開かれたのかを考えています。
もしかしたらあなたは、アダルトチルドレンとは、いったいなんなのかを知りたいと思っておいでですか。
それとも、なにか生きにくさを抱えて、藁をもつかむ思いでここを訪れたのでしょうか。
このページが、何か具体的にお役に立つことができるならと願っています。
まずはじめに、アダルトチルドレンという言葉の生い立ちをお話しましょう。
◆アダルトチルドレンという言葉、どうやって生まれた?
1970年代の中頃、アメリカで、ひとりのソーシャルワーカーが病院でアルコール・薬物依存症者の子どもの援助にあたっていました。
しかし、ひとくちに子どもといっても、小さな子も、ティーン・エイジャーも、成人に達した子どもも依存症者の家族にはいたのです。
そこで彼女は、小さな子どもたちの集まりを「ヤング・チルドレン」のグループ、10代の集まりを「ティーンエイジ・チルドレン」のグループ、そして大人になった人たちの集まりを「アダルト・チルドレン」のグループと名づけ、それぞれにプログラムを提供しました。
これがアダルトチャイルドやアダルトチルドレンという言葉が生まれた背景。
要するに、「問題状況の中を一生けんめい生きて大人になった人」という意味なのです。
(アルコール・薬物依存症者のいる家庭で育った人に限らず、ギャンブル問題、DV、家庭内の秘密、極端な厳格さなど、さまざまな問題や虐待を含みます)
こうした中を生きのびたアダルトチルドレンは、大人になってからさまざまな生きにくさを抱える場合があることが、次第に明らかになりました。
◆もっと楽な生き方ができる
さて、先ほどの話でアダルト・チルドレンのグループを始めたソーシャルワーカーが、クラウディア・ブラックです。彼女はAC概念の生みの親として、回復ステップを次のように提唱しています。
1 過去(子ども時代)を探る
2 過去(子ども時代)と現在をつなげる
3 自分の中にとりこんだ信念に挑む
4 新しいスキルを学ぶ
その中身についてはのちにくわしくご紹介しますが、大切なことは、今の生き方が苦しいとしたら、それは変えられるということです。
ここで、このページの冒頭にある象のイラストの由来をお話ししておきましょう。
サーカスに連れてこられた小象は、足に鎖をつけられます。どんなにもがいても鎖はとれません。こうやって小象は自分が非力であることをとことん思い知らされるのです。
やがて小象は育ち、足の鎖はロープに、そしてスカーフに替わります。
でも象は大人になっても、幼いころに擦り込まれた鎖のイメージにとらわれ、逃げることができないと信じています。
ACもこの象と同じで、幼いころに擦り込まれた自己イメージに今も縛られているのです。
でも、私たちの足にもう鎖はありません。私たちは自分の力でどこへでも行けるのです。
このことを心の底から信じられるようになることが、ACにとっての回復だと、私は思っています。
ご自分の中にいる「小象」=インナーチャイルドをかわいがり、勇気づけてあげてください。
(くわしくは『アダルト・チャイルドが自分と向きあう本』7章をお読みください)
こちらのページもご覧ください
-
書籍
人の責任まで背負い込んで人並み以上にがんばろうとするのではなく、「自分自身を幸せにできる人」が本当のおとな。 そのためには、子ども時代の痛みを癒し、過去のパターンから抜け出すことが必要です。 AC(ア… -
通信講座
境界とは、自分と他人とを分けるラインのことです。 どんなに親しい友人でも、夫婦や親子でも、適切な境界が大切。 <通信セミナーI 境界と人間関係>では、自分の境界に気づくことからスタートして、周囲の人間… -
通信講座
「わたしメッセージ」=I(アイ)メッセージ。 自分を主語にした言い方のことです。 <通信セミナーII 「わたしメッセージ」と感情>では、自分を主語に話すかんたんな練習から始めて、感情に気づくこと、気づ… -
通信講座
セルフケア=自分で自分をケアすること。 言葉で言うのは簡単ですが、実行するのは案外むずかしいのです。 援助職も「他人の面倒をみる」ことには慣れていても、「自分の面倒をみる」のは苦手という場合が多いもの…